| 1 | 受験勉強について | |||||
| (1) | 学習について. | |||||
 |
学問に王道なし。 今まであらゆる人が、ラクして成績を上げる方法に挑んできたが、 ことごとく失敗に終わっている。 継続は力なり。 1点を笑うものは1点に泣く。 先生の話しを「聞いたり」「見たり」はすぐに忘れてしまう。 脳はそのように出来ている。 それより自分の手で「書くこと」である。 先生の説明をただ座って聞くのはラクだが、 自分の力にはならない。 先生の話しを聞いただけで、力がつくのは、 上位7%の秀才の生徒だけである。 聞くだけで力のつく生徒は、教えていてすぐ分かる。 目付きが全く違う。恐い。 一夜漬けの勉強はやめること。 1日たったら大体は忘れている。 3年間かけて覚えた知識は、 忘れようとしても3年間は忘れられない。 問題を自分であれこれ参考書を捜しながら、 解いていくのは非常にしんどいが、 こういうしんどい目をしないと自分の力にはならない。 聞いて楽して得た知識より、 自分で調べた知識の方がはるかに身につく。 (悪銭身につかずと同じ) 教えてもらったものと、自分が失敗して覚えたものとでは、 価値が全く違う。 自分でやる気を起こして、 自発的に勉強したものでなければ、 あるいは、必要に迫られて自分で苦心して学んだものでなければ、 決して身につかない。 自分がコツコツと努力したかどうかの結果は、 点数に表れている。 どんな教科でも、分かれば分かるほど楽しいものである。 もし、楽しくなければとっくにそんな教科は存在しないはずである。 しかし、その分かるまでは、 苦しんで苦しんで努力しないと 分かるようにはならないのである。 毎日コツコツと勉強をしてもすぐに成績は上がらないものである。 しかしあきらめないで努力を続けると、 ある日突然、 目の前が開けたように分かったという実感を体験することが出来る。 植物だって、芽を出して茎を大きく成長させる前に、 根を広く張るための時間が必要である。 |
 |
||||
| (2) | 学習方法について | |||||
 |
覚えにくいところは、自分で覚えやすい方法をどんどん考えよう。 例えば、① 電流はオリエンテーリングの法則。電圧はデパートの法則。 ② Q=0.24×電流×電圧×秒は「鬼より恐い流電病」(八塚流)。 あるいは、〔大西君はAV病。〕 ③ 火成岩の種類・・・新幹線は(深花せん・は)刈り上げ頭(火流安玄) (伊藤流)。 深成岩には花こう岩、せん緑岩、はんれい岩。 火山岩には流紋岩、安山岩、玄武岩。 ④ 鉱物・・・咳する長さんうんも、かくさん奇跡の観覧車。 鉱物・・・石英、長石、雲母、角閃石、輝石、カンラン石。 ⑤ 光は密度の大きいほうへ屈折する。 ⑥ 炎色反応・・・リアカー無きK村、動力借るとするも貸してくれない馬力でやろう ⑦ イオン化傾向・・・貸そうかな(KCaNa)、まああてにすんな、ひど過ぎる借金(白金) ⑧ 元素の周期表・・・水兵離別、僕の船、なあに間があるSip (船) はすぐ来らあ。 切るかスコッチバクローマン、鉄子にどうあがいてみても、げっそり、ひっそり・・・。 ⑨ 元素の周期表1族・・・スリの仲間とルビーせしめてフランスへ。 ⑩ 2族・・・ベッドにもぐれば彼女のスリップ、バラ色ランド。 ⑪11族・・・オリンピック元素。 ⑫ 14族・・・タンスの下に現金すずなり。 ⑬ 15族・・・日本の朝は、酢豚とビールで始まる。 又は、日活ポルノ明日はサービス日。 ⑭ 16族・・・オー、すげえ世界はてんで、ポルノブーム。 ⑮ 17族・・・ふっくらブラウス、私がアタック。 ⑯ 18族・・・変な姉ちゃん歩いて来るよ。 又は、変な猫がある暗闇でくせ者に乱暴された。 ⑰ 球の表面積_4πr2・・・心配あるのに。 ⑱ 球の体積_4/3xπr3・・・身の上に心配あるのさ。 ⑲ 平清盛が太政大臣に就任・・・平清盛、いい胸毛(1167年) ⑳ 本能寺の変・・・イチゴパンツ(1582年)に本能寺騒ぐ。 1時間ずつ10日勉強するほうが、 1日で10時間するよりも効果がある。 中学生においては、毎日の家庭学習の標準時間は、 学年+1時間である。 しかし実は勉強は量より質である。 人間には、自分に不都合なこと、いやなことは忘れたいものである。 そこで、試験問題の誤答だけを記録するノートを作って正解と共に記し、 おりにふれて開いてみるのも勉強になる。 数学や、理科の未解決問題や解答をノートに貼り付け、 時々出しては眺め、少しずつ解決させていくこと。 上位生はこのようなノートを宝物のようにして持ち歩く。 |
|||||
| (3) | 理解を高めるには | |||||
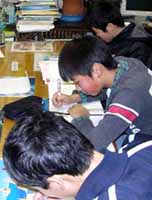 |
自分が理解できたかどうかは、友人に教えることで確認できる。 問題が分からなくて困っている生徒を見つけたら、 行ってどんどん教えてあげよう。 自分があやふやにしていた知識などが、明らかになる。 そして、いつのまにか自分に力がついてきていることが実感できるはずだ。 自分より出来の良くない友人と一緒に勉強すると実力がつく。 どんどん教えよう。 分からないことは、自分と同じ位の能力の友人に聞くのが一番良い。 友人とコンビを組んで学習するのも、成果がある。 良い勉強方法や暗記法をしている友人がいたらどんどん取り入れよう。 また逆に非能率的な勉強をしている友人を見たら アドバイスをしてあげよう。 読書のスピードを上げれば、成績も上がる。 平均は400字/分で、 偏差値55の生徒は1200字/分、 偏差値60の生徒は1600字/分、 偏差値70の生徒は2400字/分の速さで読める。 速読法を身につけられる生徒は、強い。 |
 |
||||
| (4) | 授業中の態度について | |||||
| 授業に集中できるかどうかが命である。 1日のうち最も多く過すこの貴重な時間に 友人と駄弁ったりする豪傑は、 勿論受験生とはいえない。 先生が説明しているときは鉛筆を置き、 聞くことに専念すること。 手を絶対動かさない。 同時に二つのことは出来ない。 覚えないといけないことは、 教室で全部覚えてしまうつもりで聞こう。 ノートをとって帰ってから覚えようと思っても出来ないものである。 授業中はどんどん発表しよう。 最初は間違えるのが、当たり前である。 みんなの前で恥をかける生徒は得だ、絶対忘れない。 そうして覚えていくものである。 質問の内容によって、 どれくらい勉強をしているかがすぐに分かる。 するどい質問をして先生を困らせよう。 「この問題を自分はこう考えて解いたが、間違ってしまった。 どこが間違っていますか」と、 質問できる生徒は文句なしに伸びる。 |
||||||
| (5) | 記憶について | |||||
 |
学習した知識は1時間で60%、1日で70%忘れてしまう。 (エビングハウス) 覚えたことは、そのまま朝まで起きているより、 眠ったほうが、忘れにくい。 記憶力は文字の大きさに比例して強化される。 自分の名前も大きく書こう。 記憶力は文字の濃さに比例する。 大きな文字は小さな文字より速いスピードで覚えられる。 文字は濃い鉛筆を使って、速くきれいに大きく書くこと。 カンニングペーパーは究極の暗記ツールである。 |
|||||
| (6) | 勉強の能率について | |||||
| 似たような科目は、続けて勉強しない。 数学の次には英語とかをする。 教科によって使用する脳細胞の場所が決まっているのだ。 人間の集中力が最も発揮できるのは、 脳波がα波(アルファー波)になったときである。 α波とは、心身がリラックスしたときに出るゆったりとした波形である。 頭の中が、α波で満たされた状態でないと、知識は入っていかない。 テープレコーダを活用すれば、睡眠学習ができる。 テープレコーダを早送り(2~4倍)にして聞くことを速聴という。 速聴すれば集中でき、脳波をα波にし、大脳が活性化し、 結果として、速続力、思考力、理解力、創造力等が、養われる。 勉強するときは、好きな科目は最後までとっておく。 満腹のときは頭の働きが鈍い。 血液が胃袋の方に行っているからである。 頭が活発に働くのは起きてから2,3時間後である。 1日において学習の能率は、午前10時と午後3時頃にピークになる。 昼寝を10分でも20分でもすると、1日を2倍に使える。 勉強の能率は、いかに環境を自分に適したものにするかということと、 自分をいかに環境に適応させるかということによって決まってくる。 |
 |
|||||
| (7) | 問題集について | |||||
 |
「この科目は、この参考書。この問題集」と決めたら、 受験本番までに何回読み返すか、何問解くか、 突破量の目標を立て、 この消化スケジュールを立てること。 参考書を読んだら、すぐ、それに該当する内容の問題を解いてみる。 参考書は一冊で十分。 そのかわり、その一冊を完全にやっつける。 東京大学(文系だが)に現役で合格した私の友人がいた。 彼は数学の参考書は一切使用せず教科書の問題のみを、 毎日何度も何度も真っ黒になるまで解いていた。 問題を解いた後には、次のような記号を使おう。 ENDの略。 何回やっても解けるから、もう二度と解かなくてもいい問題。 合格の略。 とりあえず解けたが、あと1回くらいは解いておいたほうがよい。 Againの略。 あと2~3回は解き直したほうがいいと思われる問題につける。 このように3段階に問題を分けておけば、 復習するときに非常に能率的である。 |
|||||
| (8) | 成績について |  |
||||
| 成績は性格に大いに関係がある。 親や先生は君達より試験の経験が豊富であることを忘れるな。 私の同級生に畳屋さんがいます。 彼は、お客さんの家へ一歩入ればその家全体がわかるといいます。 私は、数学や理科の問題を見ただけで、 この問題を解くには、どんな方法があるのか。 どんな公式を、使うのがいいのか。 どの方法がもっとも効率よく解けるのか。 この問題の出し方は、適切であるのか。 この問題は高校へ行っても応用できるいい問題か。 生徒は、どんな風に解こうとするのか。 生徒は、どこでミスをするのか。 そういったさまざまの事がすぐにわかります。 なぜなら、、生徒は初めて出会った問題かもわかりませんが、 私は(又は学校の教師は)、同じような問題をもう40年以上も、 繰り返してやっているからです。 親や先生は一番効率的な学習方法を知っている。 親や先生の言うことを、素直に聞く生徒ほど伸びる。 親や先生は君達にいろいろと期待するからこそ、あれこれ言うものだ。 このことに反抗したところで、得るものは何もないのではないかな?。 学校生活や家庭生活や友人関係が落ち着かない生徒は、 学習に集中できない。 人並みの頭をもっておれば、 熱意・根気・センスがあれば、必ず合格する。 (みんな根気が無いんだよねえ) 勉強は、元気とやる気と根気、この3つの気で楽しくやろう。 成績は、思考力、暗記力、感性で決まる。 しかし90%以上は暗記力。 思考力、感性は個人差があるが、 暗記力は勉強のやり方次第で誰でも身につくはず。 頭が良いからといって成績が良いとはかぎらない。 頭の良い人より努力すれば追い抜くことは当然可能である。 頭の良い人は、足の速い人がいるように確かにいる。 しかし最後は努力を積み上げる人に、いつかは必ず追い抜かれる。 |
||||||
| (9) | 生活態度について | |||||
| 自ら計画を立てて、学習できる人が最後は勝つ。 親や先生に言われて勉強しても、大して身につかない。 「君は、それでいいのか」と言ってくれるもう一人の君がいるはずだ。 毎日が、そう言ってくれるもう一人の君との闘いである。 「楽しくやろうぜ」と、誘ってくる自分に負けるな。 上位生に共通して言えることは、 「自分は誰のために勉強しているのか? 紛れもなく、自分自身のために勉強するのである。」 という確固たる自覚が彼らにはできあがっている。 それに対して、 「両親のために勉強させられている」 生徒が下位生に多い。 自分の頭を信じよう。 そして自分の頭で考える。 努力は君達を裏切らない。(越智投手) 「必ず合格できる!」と思うことが、成功への第一歩である。 目標のない勉強は、 バーのない高跳びのようなもので力を出し切れない。 失敗の多い人ほど、いざというときに実力を発揮できる。 なんでもすらすら理解できる子よりも、 疑問の多い子のほうが将来伸びる。 志望校をみんなに公言して、自分にプレッシャーをかけよう。 机の前にも大書して貼りつけよう。 もしも失敗した時には恥をかくような状況を、意図的に作り出すこと。 でないと普通の人間は怠けてしまうものである。 (もし失敗した時は、「ちょっと望みが大きすぎちゃった」と みんなと一緒に笑える大きな人間になりたいものだ。) 勉強は、99%の生徒にとっては苦しさを伴う。 しかし、その苦しみの後に、必ず楽しさを味わうことができる。 人間は、コツコツと努力するのが一番大切である。 頭は良いが努力しない生徒より遥かに立派だと思う。 頭脳はずば抜けていいのに、口だけで何もしない人間が多い。 こんな人間ほど始末に困るものはない。 試験に向けて努力することが一番大切である。 勉強もしないで試験を受けるのは、時間とお金の無駄である。 上位生の学習は、 よく締まる(集中する)、弛む(遊ぶ)の交代作業である。 つまり、途中で息を抜いたり環境を変えたり 筋肉を動かしたり学習以外のものに没頭したりする時間がないと 集中力も学習密度も頭の回転も全てに故障が起きてくる。 自分の部屋や机の周りはきちんとしているか。 自分の机に座ったときが一番落ち着くように部屋を飾ろう。 試験前日になると、ほとんどの生徒が、 「もっと前から受験勉強を始めていたら良かった」と泣きが入る。 さて君は大丈夫だろうか。 全てのことや人間には、プラス面とマイナス面がある。 マイナス面しか見えない生徒は伸びない。 プラス面を探す努力をしよう。 マイナス面は誰でも見える。 家の中でも、家族の一員として、 家事手伝い等の役割分担をしっかりしていて、 家族のために行動できる生徒は必ず伸びる。 学校や学級の係り活動や清掃等の奉仕活動は 真面目に一生懸命しよう。 そうすることによってクラスの仲間からの信頼を得ることができる。 そんな生徒は必ず伸びる。 Please 参加 to 学校行事 with 積極的 as 自ら取り組む。 And you have nothing from 精神 of いやいや。 There is nothing except 無駄 of 時間。 Desukara you must have + 思考 to 何事。 |
  |
|||||
| 学校では自分さえ良ければいいのではなく、 クラスのために何ができるのだろうかと考える生徒は必ず伸びる。 またそれよりも学校のために何ができるのだろうかと 考えられる生徒はさらに伸びる。 自分だけの世界から、もっと大きな社会のためにと、 だんだんと世界を広げて物事を考えられる、 そんな心の広い生徒ほど伸びる。 |
 |
|||||
|
この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、unison_i@yahoo.co.jpまで電子メールでお送りください。 | |||||




